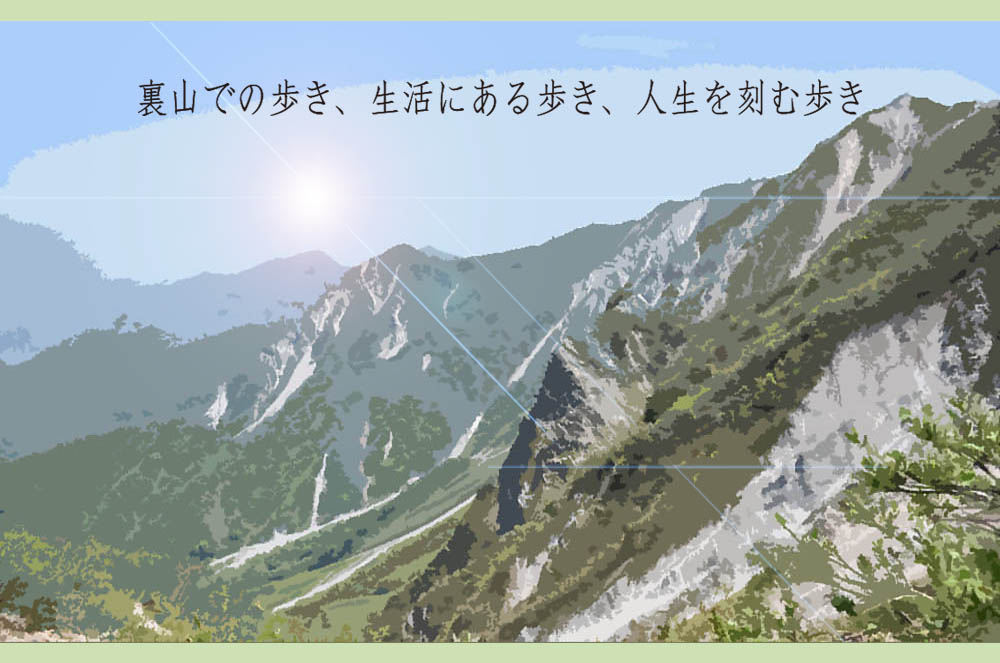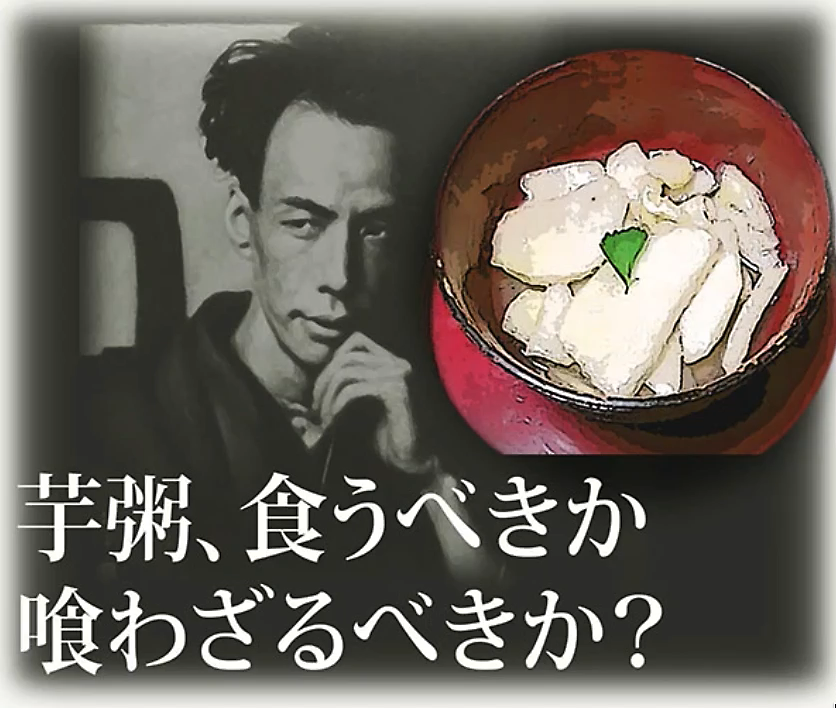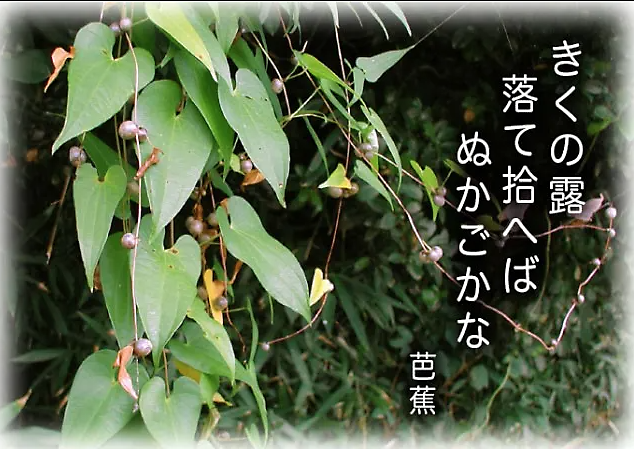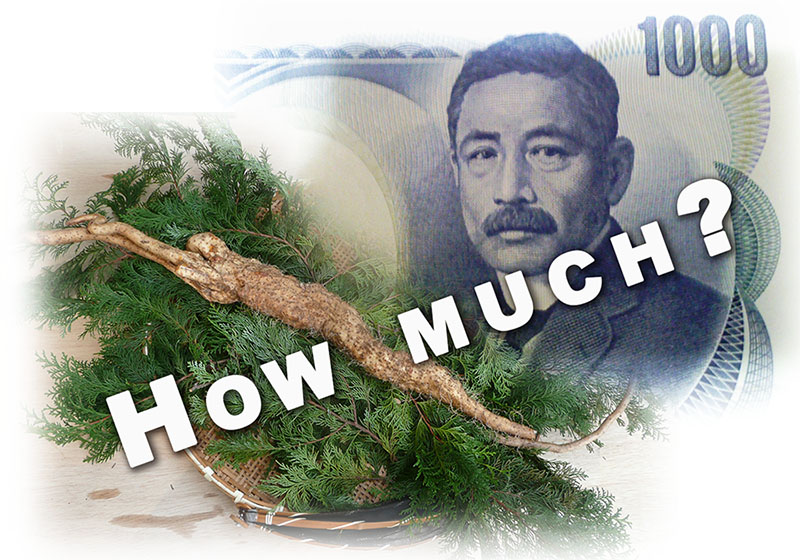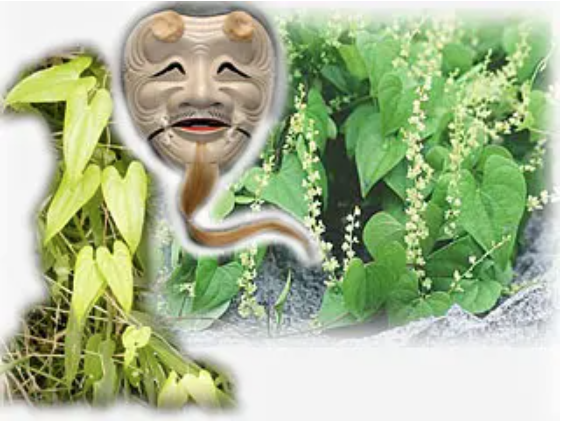このカテゴリーは、日本原産種の山芋・自然薯(自然生)生産団体に携わっていた頃の記事を中心に、折々のイベント、古き文人たちと山芋の関わりなどを歳時記風に記したものを集めています。
春山淡冶にして笑うが如し
夏山蒼翠にして滴るが如し
秋山明浄にして粧ふが如し
冬山惨淡として眠るが如し

山滴る季節、御縁の皆様方におかれましては・・・、と時候の挨拶にも使われる「山滴る」は俳句の季語でもあります。この言葉は中国、北宋(960年~1127年)の山水画家・郭煕の言葉で、「四時山」という漢詩が原典のようです。
日本では、正岡子規が初めて俳句に用いて夏の季語として使われるようになったとも言われています。因みに「山笑う」「山装う」「山眠る」もそれぞれ春、秋、冬の季語になっています。
山を巡りその四季の風情を追い求める輩にとって、これほど簡潔でぴったりな言い表しには全く脱帽するところで、山の幸「自然薯(自然生)」にとっても、これはまさしく自らのフィールドを言い得て妙と納得するに違いありません。
早春、地中で眠っていた山芋も、山面の萌えた感じ、淡冶(たんに)さに微笑んで、地上へ芽を押し上げて来きます。そして、この頃(夏)となれば、草木の瑞々しさが辺り一面に滴り、たっぷりの陽光を求めてツルを精一杯に伸ばし、葉を茂らし始めます。

そして、多くの植物がそうであるように、山芋たちも秋に向けて花を咲かせて実を付けます。その装いの秋になってからようやく地下では、芋部が太ってきます。冬への準備が始まるのです。たっぷり夏秋のエネルギーを栄養として蓄えます。
太古より、人為的な栄養がない山中の腐葉土で育ってきたじねんじょう山芋は、栽培の畑でも同じく人為的な栄養や、有機でもあってもその栄養過剰を嫌います。水と光と空気というシンプルな三要素で、肥料なしでも逞しく育つのが本来の姿です。その野生の元気さが、外来のひ弱な野菜たちと違う所でしょうか。
そして、準備を終えた山芋たちは、ツルを自ら切って地中で長い冬を眠って過ごすのですが、この当りで人間様やイノシシが都合良く登場して、その豊かな恵みをいただいてしまう訳です。ところが山掘り人もイノシシも心得たものです。ちゃんと春には芽が出るよう首部を残しておく知恵があります。
イノシシの食い残し、ガリガリ齧られ傷ついた芋からでも、腐らず春には芽を出します。その元気さこそ、今日よく言われる健康機能性の素がぎっしり凝縮されている由縁なのでしょう。実に有難い植物です。


■山芋人物歳時記 関連ログ(2021年追記)
・小説「坊ちゃん」の正体・・・(弘中又一)
・小説「吾輩は猫である」自然薯の値打ち(夏目漱石)
・零余子蔓 滝のごとくにかかりけり(高浜虚子)
・貴族・宮廷食「芋粥」って?(芥川龍之介)