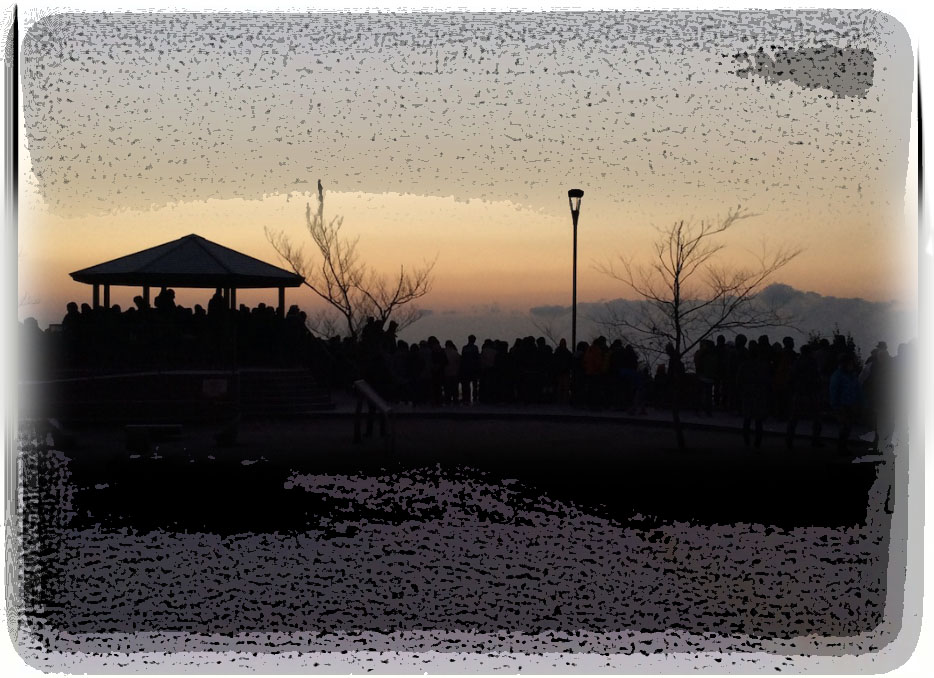
私たちの遊歩に観客はいるのか?
大きな岩塊によじ登って、ピークを踏みしめたなら、360度の景色をじっくりと確かめながら達成感と高揚感をもって飽きることなくその風景を眺めることでしょう。誰だってそうでしょう。しかし、同時にそのえも言えない神々しい光景の向こうから、逆にピークに立っている私を見つめているモノを感じたことはありませんか?
日常では見ることのできない雄大で厳かな風景を鑑賞しにやってきた観客であるはずの私は、同時にそれを実現したパフォーマーでもあります。一人っきりの私のパフォーマンスは、誰にも気を留められることがありません。観客の居ない一人芝居のようなものですが、「よくやってきたね」と労う大自然の時には厳しく、時にはやさしい眼差しをどうしても感じることがあります。向こうからも見つめられているのです。そうやって互いが向き合っている関係が、溶け合って一つになる至福の感覚がそこにはあります。まあこれが山登りの最大の目的といえるでしょう。
つまり、私たちの山歩きシーンには、観客が必ず何処かにいるということです。それは樹々であったり、小鳥やけものであったり、風雨であったり、様々な自然の様相で私に眼差しを送って交歓してくれます。それは決して険しい山岳だけではありません。自然と触れ合えるところならどんな場所でもそうだと思います。ビルに囲まれた街中であっても、フト見上げたその先の青い空に白い雲が流れていれば、きっとそれに慈しむような眼差しを感じるでしょう。それが山上から眼下に広がる雲海と対話した経験のある方にとっては、一層心に響くものでしょう。下から見上げる雲の向こうにはピークに立ちすくんでいるもう一人の自分とも対面しているのです。
人それぞれに、心を通じ合える裏山や、刺激や感動を分かち合える山岳との出会いがあるでしょう。そういった舞台(ステージ)で得た体感や感性を、日常に持ちかえって育むことによって、峰々とは程遠いステージにあっても自分の立ち位置を確かめることができて、自らの歩きの舞台を押し広げていくことができるものと信じています。

私の初期の歩きの舞台となった六甲山は、日本各地のどこにでもあるようなごく普通の背山です。(「遊歩の舞台としての六甲山とは」も参照ください)それも山脈とまで言えないような狭いエリアで1,000mを超えるピークもない山系(最高峰:931.3m)です。すぐ麓には神戸・大阪間の都市がぎっしりととり囲み、多くの住民を抱え込んでいます。国立公園のエリア内においても観光化が進み、自然もいたんでおり、かなり俗化された山域だといえます。ドライブウェイを始め、ケーブル、ロープウェイ数系統などによる山上へのアクセスも整備され、植物園、博物館、牧場、スキー場、ホテル、レストラン、ゴルフ場(日本最古)別荘群、郵便局、小学校などの行政施設も整った都市機能があるというか、もう都市そのものでもあります。
エマージェンシーにおいても、危険生物や困難ルートも際立ったものはなく、山上の気象も年間を通して穏やかで、常識的な装備で注意して歩けば、さほど技術を要求されることもありません。迷った時は、山上方面へ向かえば必ずドライブウェイに出会うし、下山を選べば、どこかしらの市街地に数時間でたどり着くことができます。
しかし、1,000mに届かない標高とはいっても、南山麓はほとんどが急斜面となっており、アプローチ地点が海抜20~50mといった地点から始まることを考えれば、内陸地の1500~2000m級と変わらない実標高差を登ることになります。(伯耆大山1,710m:実標高差930mなど)簡単に低山とは侮ってはいけないでしょう。逆に六甲山を歩き慣れた方は、2000m級の山岳においても体力的な問題はないと思います。
六甲山に深奥幽玄はあるか?
この点では日本各地の都市近郊の山系は大なり小なり似たようなものかもしれません。さて、我が裏山もこのような紹介であれば、何も遊歩においてもさほど際立つ特色があるようには思わない舞台(ステージ)ですが、「遊歩」がより遊歩のステージとして鮮明に浮き上がる重要な条件、他の山域にはあまり類のない条件を考えてみましょう。
それは、やはり山麓の周囲一帯に拡がる「巨大な都市圏」というものの存在が外せないようです。東西南北から圧倒的な市街地化の波を受け、緩やかな山麓のほとんどがゾンビに襲われれたように侵食され、建造が許されるギリギリの斜面まで市街化が進んでしまっています。山上周辺の観光化も前述の通りです。自然の保全という点では、ほとんど六甲山系は満身創痍といえます。六甲山には幽玄深奥というような(異空間的な)自然と残念ながら、ほとんど出会うことはありません。「六甲山で一体、在るべき自然がどれだけ残っているのか?」と訊かれることがあります。答えに窮しますが、未開のジャングルや未踏の深山のような状態を自然というなら、そういう自然は残念ながら、このエリアにはほとんど見当たらないでしょう。近代に至るまでに平安の源平合戦、戦国時代に繰り返された戦火で多くの樹木は伐採され、禿山となっていました。現在の植生の多くは明治以降の植林事業によるものだし、沢のほとんどが都市を守る名目で進んでいる堰堤100年計画で、谷は砂防ダムだらけ、都市化のあおりでクマ、猿、鹿などの野生の動物も去っていきました。この地でどれだけ自然のリアルと出会えるものでしょうか? 私たちのウィルダネスに果たしてなりうるのだろうかという疑問はぬぐえません。
しかし、山麓に数百万という住人(ほとんどが都市生活者)を抱え、この自然と不自然がせめぎ合い、都市化の脅威と侵食をこれほど受けつつも、なおかつこの山系が 独自の自然の秩序を保ち得ているのは確かなことです。不思議なことですが、せめぎ合う近さに因る六甲山特有の厳然とした自然が在るのです。それは、時には父親のような凛々しい威風で、自然の何であるかを教えてくれますし、時には母親のような優しい慈愛を持って私たちの歩きを包んでくれます。そう感じるのは私だけでしょうか。
それは高い山岳登山などで自然と立ち会っているときの感覚とは少し違うかもしれません。もっと身近な里と里山というような、現代ではすっかり失われしまったような距離感を感じます。
ちょっとした山岳へ遠征といえば、はやり長いアプローチが必要で、その途中に都会の日常生活の緊張感から徐々に解きほどかれ、自然のフィールドへ向かう気持ちに対応していきます。そんなモラトリアムが与えられますが、六甲山では、そんな間がなく、登り口からいきなり自然空間へジャンプします。そういうワープ感覚が何といっても、この山系の醍醐味でしょうか。真冬なら、朝、スタバで熱々のコーヒーをすすって、昼までにはもう有馬の百間滝の氷壁を登っているってことも可能です。この山域は、自然の営みがコンパクトに納まっていて、日常の生活感からの落差を生む距離感も手伝って、私たちの感性に響きやすいところがあるようです。「トンネルを抜ければそこは北国であった」じゃないですが、一歩踏み入れば、そこそこの稜線歩きや沢歩きのコース、クライムコースなど、近しい自然に囲まれます。そして、一歩踏み出るだけで、もう都会のど真ん中という体験に見舞われます。一種のワンダーランドです。このワープ感覚が味わえることに、この六甲山のステージ(舞台)としての本領があるのでしょう。

水の〝リアル〟と出会う
新幹線・新神戸駅のホームのすぐ下に渓流への入り口があります。芦屋川の表銀座ルートと並んで人気ある摩耶山・再度山への玄関口です。この下流はすぐコンクリート護岸となって、港まで街の中心を流れ神戸港へとそそぐ二級水系です。この水がどこから流れ出てくるのだろうか? などと都会の住人たちはあまり考えもしないのですが・・・。この流れを辿ってみると様々な水との触れ合いを体験することができ、そのリアルさを体で感じることができます。
コンクリート護岸を流れる川にはホタルも居ないし、ましてやその水を直接に飲もうとは思いませんが、すこし上流に遡ると、もう流れは渓流となって、30mを超える布引の滝の瀑布がミストになって私たちにふりそそぎます。そのすぐ先には日本最古の大型コンクリートダムがあって、市ケ原のキャンプ場へと続きます。そのあたりから流れの中に足を入れたくなります。そこを抜けると、ツエンティクロス(二十渉)といわれる水際にそった長い渓流を辿る間にたくさんの枝谷から流れ込んでくる水を見ます。この辺りでは、水は本来の水です。なんのためらいもなく頭から浴びたり、飲み干したりしています。本谷が狭まってくると、歴史古道の徳川道から流れが急になる桜谷に入ります。ちょうど上高地から梓川を遡って横尾から涸沢に回り込む感じのミニチュアコースでしょうか。距離は半分くらいで、景観の迫力には負けますが、水に触れ合ったり、流れのリズムなど身近な体感はこちらは負けません。
少しづつ流れは細まって、登りもきつくなり、ゴールの近さを感じさせます。そこを更に源頭に向けて詰めていくと、摩耶山直下にたどり着きます。そこでチョロチョロと湧き出してくる水を目にして、そっと手のひらにとって口にすると、もう理屈抜きで水のリアルさをそのまま飲み干すことができます。

大阪湾へ流れ出した沢の水が、海上で温められ蒸気・大気となって雲を作り、六甲の峰々の上で雨になったり、露になって山地に戻ってきて、流れを集めてまた海へと帰っていきます。自然が永遠に繰り返している循環です。ここでは、そういうことが何気なく半日ほどの時間でコンパクトに体験できるのです。このように感じ得たリアリティが、また都会の生活でも反映してくるのです。
ビル群の一室で、カルキ臭くなった水道水と出会う。しかし、その水の源流を知る者、沢を登り詰め岩の間からわずかに滴る水を一度でもノドに通したことがある者にとっては、水が何であるのか、自然の何であるか、また同時に不自然の何であるかを十分に知ることができのです。壁に囲まれた部屋にあっても、そこで飾られた一輪の花に豊かな自然を感じることができる人ならば、その部屋には自然が広がります。風であれ雨であれ然りです。そういった感性を培っているか、わが内にある自然が問題なのです。
話は少し逸れましたが(「資料3:引き裂かれた六甲山」の項目にあるコリン・フレッチャーの言葉も味わってください)自然と不自然が圧倒的にせめぎあっている状態がこのエリアのいたる所にあります。そういうことを肌で感じることによって、逆に、都会における生活の中でリアリティの乖離を受け止めやすくしてくれます。そんな不思議なバランスを教えてくれることが六甲山という舞台の大きな特徴だと思います。
NEXT ▶︎ 読本8:一人歩く時ほど孤独より遠い?
BACK◀︎ 読本6:ウォーキングは健全なる狂気である?(遊歩大全)
★読本:遊歩のススメを冒頭から読まれる方はこちらをクリックしてください。
